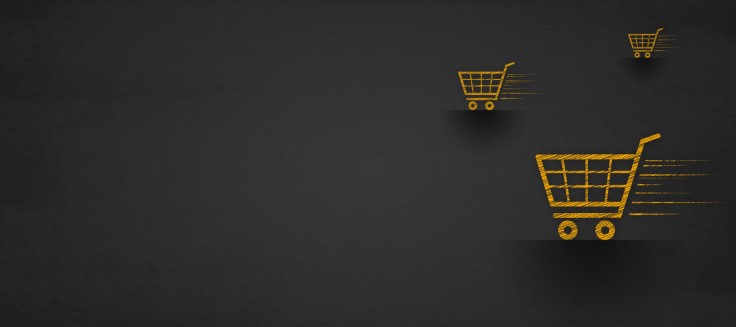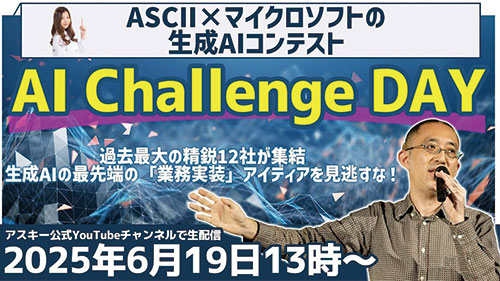第1章 放浪息子、商人になる。

 放浪息子
放浪息子
 商人父
商人父
「息子よ、私はもうダメだ。人気アイドルちゃんが実は、○○だったなんて… 店は任せたぞ… う、ガクッ」
「商人父!商人父~~~~~!!!」
~ こうして、放浪息子は商人父の後を継ぎ、商人となった。 ~
第2章 門出

 放浪息子もとい商人
放浪息子もとい商人
 友人
友人
「とんでもなくどうでもいい理由で、父は現役を引退し、僕が店を継ぐことになってしまった。。。」
「よう、放浪息子!どうした?柄にもなく考え込んじまって。馬みたいな顔が、まるで、ロバみたいだぜ。」
(どっちにしろ、馬面じゃないか。)
「それが、商人父がどうでもいい理由から隠居してしまって。今店を継いでしまったとこなんだ。」
「ほう、そりゃおめでとう。それじゃあ放浪息子ではなく商人ということか」
「もうちょい、放浪息子でいたかったんだけどなあ」
「それで、商人父はいったいどんな理由で、隠居してしまったんだい?
あんな元気だけが取り柄で商才皆無のダメダメ商人が隠居するなんて相当の理由だろうに。」
「それがカクカクシカジカで。」
「ははは、商人父はバカだなあ。人気アイドルちゃんが○○だったニュースで隠居とは。○○なのがむしろいいのに。」
「え!?」
「え?」
「いやあ、世の中には色々な趣向の人がいるもんだ。
さてさて、人気アイドルちゃんの話はおいておいて、店のことは考えなくちゃなあ。
商人父の代ではパッとしなかったけど、僕の代では大きくしたいなあ。
まずはともあれ、店の状況を確認しないと始まらないか。」

 商人
商人
「閑古鳥が鳴くとはこのことなんだろうな。お客のなんてきやしない。」
「このままではだめだ、商売の方法を調べなくては。」
「商人父は商才ゼロであてにできないから、先輩商人に話を聞きに行こう。」
第3章 先輩商人の話はとにかく長い

 商人
商人
 先輩商人
先輩商人
「先輩商人!」
「どうしたんだ。放浪息子、いや、今は商人か。」
「先輩商人、僕に商売のイロハを教えてください!」
「手と腰はしなやかに。それでいて力ずよく踊るのがコツだ。」
「”アロハ”ではなくイロハです、先輩商人!」
「ほほう。商売のイロハとな。商売敵の私に聞いてくるとは、よほど切羽詰まっているとみえる。」
「う、それが、反論のしようがないほどでして。」
「よろしい。まあ、何かと商人父とは互いのトレジャーを交換し合った仲だ。手ほどきをしてやろう。」
「ありがとうございます。(商人父よ、何をしたか知らないがGJ!)」
「それでは、この街の商売を説明しよう。」
「よろしくお願いいたします!」
「まず、この街で商売をするには、店が必要だ。」
「そして、店舗には、4つの種類がある。『寄合店舗』、『小店舗』、『大店舗』、そして、この前できたばかりの『NEW TYPE』だ。」
「4種類...しかし、最後のはなんだか、鋭い感覚をもって会話までできちゃいそうな名前ですね。」
「残念ながら、ガ〇ダムとは何も関係ない。」
「して、先輩商人、これらは何が違うのでしょうか?」
「うむ、よい質問だ。各店舗はパラメータが違う。」
「パラメータが違う…」
「店舗には4つのパラメータがある。4種類の店舗の各パラメータは次のようになっている。」
| 店舗タイプ | 初期費用 | 維持費 | 商品棚数 | レジ数 |
|---|---|---|---|---|
| 寄合店舗 | 5G | 売上の25% | 5 | 1 |
| 小店舗 | 10G | 2G | 2 | 2 |
| 大店舗 | 10G | 15G | 7 | 7 |
| NEW TYPE | 15G | 客数 × 1G | 3+ | 1+ |
「商人、初期費用とはなんだかわかるか?」
「新しく店舗を立てるときに必要な費用でしょうか。」
「そうだ。維持費については後で述べるとして、『商品棚数』と『レジ数』について説明しよう。」
「『商品棚数』は、仕入れられる商品の最大数を示している。各店舗は商品棚数以上に商品を仕入れることはできないのだ。」
「『レジ数』は、一度に処理できる商品1種類あたりのお客さんの数を示している。各店舗は、商品1種類あたりにつきレジ数までしかお客さんを同時にさばけない。」
「なるほど。レジ数が少ないと機会損失を招くわけですね。」
「その通りだ。」
「それでは、『商品棚数』も『レジ数』も多いに越したことはないと。」
「ああ、間違いない。
間違いないのだが、商品棚数とレジ数が共に多い大店舗は維持費が高い。
ここで、さっき説明を飛ばした維持費の話をしよう。
我々商人は1ターンの間に商品を仕入れる。そして、全てのプレイヤーのターンが終了した後に『決済』を行う。
決済では、商品をお客に売り、利益を得る。
利益は所持金に加算され、次のターンでより多くのものを仕入れることができるようになる。もちろん増店もできる。
そして、利益は店の売上げから維持費を差し引いたものになる。」
「維持費が高くなると利益も減ると。」
「そうだ。そして、商品棚数とレジ数が多く有利な『大店舗』は維持費が高い。しかも、売上げがなくとも維持費を支払う必要がある」
「なるほど。店舗選びもケースバイケースなのですね。」
「そのとおりだ。
店舗の話としては、もう一つ付け加えておくことがある。」
「何でしょう?」
「『NEW TYPE』の話だ。」
「そういえば、商品棚数やレジ数に『+』がついていますね。」
「まさにその話だ。このNEW TYPEには他の店舗にはない特徴がある。」
「ゴクリ…」
「なんと、ターンの終了時に商品棚数とレジ数が増加する。」
「な、なんだってー(小並感)」
「まあ、これは使ってみればわかる。」
「さて、次は商品について説明しよう。」
「よろしくお願いします!」
「まず、この街には7つの商品しかない。」
「少ない!」
「ゲームを簡潔にするためだ致し方ない。」
「先輩商人、発言がメタいです!」
「気にするでない。」
「...」
「7種類の商品とその価格は次のようになっている。」
| 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|
 |
小麦 | 1G |
 |
野菜 | 2G |
 |
果実 | 5G |
 |
乳製品 | 8G |
 |
肉類 | 10G |
 |
雑貨 | 10G |
 |
宝飾品 | 20G |
「価格が1つだけですが、仕入れるときも、売るときも同じ値段なのですか?」
そうだ。作成者はこのゲームをボードゲームとして作ったのだが、仕入れ値と売値を別々に設けると計算が面倒だからと言って一緒にしてしまった。我々や街のビジュアルと、商品の画像がだいぶかけ離れてるのもそのためだ。」
(またメタい...)
「深く考えるでない。」
「先輩商人、仕入れ値も売値も同じでは、利益が出ないのではないでしょうか?」
「そう考えるのも当然だ。しかし、作成者はあろうことか売っても仕入れたものが減らないようにした。
つまり、2回目以降の売値が売り上げとなる。」
「ずいぶん無理やり感がありますね。」
「数字の分だけ難しくなってしまうため致し方なかったのだ。
ついでに売り上げの計算の仕方を教えよう。」
「店舗の時には掘り下げなかった部分ですね。」
「そうだ。
具体的な計算方法の前に、需要の話をせねばならぬ。」

「上図の需要を見てみるのだ。」
「商品が7枚あります。」
「需要は、必ず7枚で構成される。つまり、この7枚にある商品が売れる商品だ。」
また、この街では全プレイヤーがターンを終了し決算が終わるまでを四半期と呼ぶ。
そして、四半期の初めに必ず需要は変動する。
売上げの計算方法は基本的に、需要商品の枚数×店舗の該当商品数×商品単価だ。」
「それでは、上図では私は果実を2つ仕入れているため、2 × 2 × 5G = 20Gが売上げでしょうか?」
「基本はそれでいいのだが、忘れてはいけないのが、店舗のレジ数だ。」
「レジ数=一度に処理できる商品1種類あたりのお客さんの数でしたね。」
「そのとおりだ。だからこの場合、1 × 2 × 5G = 10Gの売上げが正しい。そして、維持費の2Gを引いて8Gが利益になる。」
「なるほど。店舗の2つのパラメータがだいぶ効いてきますね。」
「何が良いかは、自身で考えてみるのだ。」
「そして、重要で残酷なことを1つ教えよう。」
「何でしょうか?」
「それは、市場シェアだ。」
「市場シェア...」
「お客は、市場シェアの上位2名の店でしか、その商品を購入してくれない。」
「ざ、残酷だ…」
「市場シェアは保有するすべての店で仕入れたその商品の数で決まる。つまり、たくさん仕入れろということだ。」
「肝に銘じておきます。」
「これで基本的な事柄については説明した。このほかにも、『1ゲーム=12四半期=Y1Q1-Y3Q4まで』や『小麦は必ず需要が2枚ある』、『アクションカード』があるがこれらは実際にやってみてその効力を体感するのが良いだろう。」
「さあ、下の『GAME START』でゲーム開始だ!」